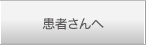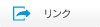眼科医局について
教授挨拶
 奈良県立医科大学眼科学教室のホームページへようこそ。
奈良県立医科大学眼科学教室のホームページへようこそ。2025年4月より教室を担当させていただきます加瀬 諭(かせ さとる)と申します。
奈良県立医科大学は昭和20年に発足した伝統と歴史ある教室です。多くの先輩方の功績により、これまで多くの患者さんの失明予防に貢献してきた事は言うまでもありません。
そのような恵まれた環境を背景に、教育・診療・研究を推進しております。
学生教育は、学生に眼科的知識を教授するだけでなく、マイクロサージェリーの醍醐味を体験させる豚眼実習、手術見学、眼底写真や光干渉断層計などの種々の眼科機器の検査体験の実習を実施し、眼科的所見とともにMRI画像などの画像所見の読影の重要性を提示したいと考えます。
眼科研修医の教育については、外来業務においては、その日に受診した新患の症例をその日のうちに上級医とともにフィードバックさせ、眼疾患の検査や診断を習得させる機会を作ります。定期的に教室員皆で難症例について討論をし、いかなる眼疾患の患者さんも最善の治療を提供すべく努力しております。併せて、症例報告や原著論文を執筆させることにより、単に研究会や学会での発表経験だけでなく、報告した症例の背景や診断、病態理解を深めることが可能になります。
手術教育としては翼状片や結膜腫瘍の再建、外来での霰粒腫切開などの小手術、眼瞼下垂・眼瞼内反症手術、水晶体再建術を習得させ、上級医とともに術中の手術ビデオによる振り返りを行います。術中に採取された、全ての生検や切除検体を病理検査へ提出し、その手術症例において発生した病理組織学的所見を、眼科医の立場からも教室員と検証し、臨床像の理解を深めたいと存じます。
大学院教育では、可能な限り研究に専念できる環境を作り、大学院生に安心して医学博士号を取得させるべく、新規性のある研究課題を立案します。ちょっとした生命現象を大切にし、なぜその様な現象が起こるのか?という問いを持つ様に指導していきます。そして、基本的な実験手技の修得だけでなく、仮説と検証、データの解釈や構築といったサイエンスの基本的な考え方も教育したいと思います。加えて、関係各科ひいては本学と交流のあるミシガン大学等海外の研究機関とも連携し、留学も推進して参ります。
診療面では、失明に直結する網膜硝子体疾患、緑内障、角膜疾患を中心に診療しております。加えて複雑な病態を呈する斜視等の小児眼科疾患、神経眼科疾患も精力的に治療を行っております。眼科学の診断・治療は非常に多岐に渡っておりまして、本学ではあらゆる眼疾患を治療すべく体制を構築しております。
私は病理学の大学院を修了したこともあり、眼病理学(Ocular pathology)を基盤に、ヒトの眼疾患に関わる臨床病理学的研究を中心に行ってきました。眼病理学は、腫瘍だけでなく眼部に発生するあらゆる疾患が対象となります。眼腫瘍は結膜や眼窩等の眼付属器のみならず、眼内にも発生します。眼腫瘍はこれまで稀な疾患と考えられてきましたが、本邦における高齢化や紫外線量、診断技術の向上等の影響により、悪性腫瘍の診断頻度が増しています。腫瘍は形態学的には隆起性病変を呈することが多いですが、その鑑別診断には炎症や変性疾患など多岐に渡ります。適切に診断をするためには、試験切除の可否を含め、幅広い疾患に関する基礎的知識と病態理解が必須となります。腫瘍切除術に際しては、眼付属器腫瘍では翼状片手術、眼瞼手術、眼内腫瘍に関しては水晶体再建術、硝子体手術の技量が必要になります。手術に際して得られた病理組織検体を、臨床の最前線にいる眼科医の立場からも観察し、臨床所見の考察を行っております。
2025年春からは、私は網膜硝子体外来の担当に加え、新規に眼腫瘍外来を立ち上げております。様々な眼疾患が、本学で治療可能になると考えております。
以上、奈良県立医科大学眼科学教室の現状、魅力と将来の展望を述べさせていただきました。この伝統のある本教室をどうぞよろしくお願いいたします。